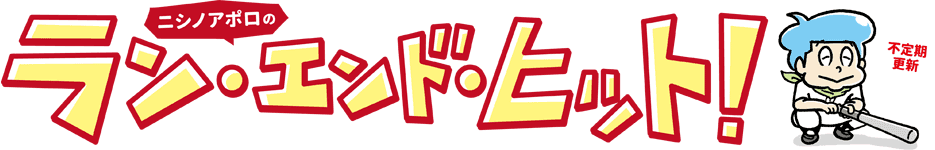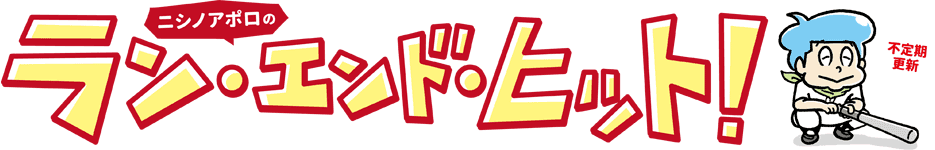| |
|
|
|
|

『復路の情感』
風が木々を揺らし、緑さざめく午後。地面に落ちる木漏れ日揺蕩う玉川上水の脇道を、その日ボクは一路公園脇の美術館を目指し歩いていた。
その訃報を知ったのは、朝のニュース番組。
率直にショックだった。そして、動揺した。
“あぁ、この人のいない世界でこれから生きていかなければいけないんだな”
寂しくて、不安で、居たたまれなくて。
それは例えば、学校やら職場やらで不意に誰か仲間が辞めて去っていってしまったときのような揺らぎ。
置いてけぼりをくらったような。浮き足立ったような。索漠とした喪失感。
物足りなくて。嘘みたいで。信じられなくて。どこか絵空事のようで。夢みたいで。
けれど何より生々しく、何より現実的で。真に迫るような。身を切られるような事実。押し潰されそうなほど、重く、堪えがたい真実。
身内でも友人でも知り合いでもない人にこんな思いを抱くのは、間違いなく自分がその人の何かを拠りどころにしている部分があったからで。受け入れ難く、ただただ哀しく、物わびしく。
勝手に思い込んでいたことだが、氏と同年代であるウディ・アレンと共に90歳を過ぎてもピンピンしてるに違いない――そう思い込んでいたのに。
とはいえ、晩年の講演に数度足を運ばせていただいた際には、博学才穎な論説に毎度感服させられるとともに、どこか訥々とした口振りから受ける確かな時の移ろいというのも明瞭で、そこはかとなく漂う翳りに胸騒ぎを覚えないこともなかった。それが実際こうやって現実のものになってしまう日がくるなんて。思いもしなかった――というわけではないにせよ、想像したくもなく、視界に入れたくなく、気のせいにしたく......。
数年前、吉祥寺の街を一人歩いている姿をお見かけもした。
駅前、若者がたむろするアイスクリーム屋の前の歩道をゆっくりと、静かに、生気なく、それでいて寂しそうに、遠くを見つめながら陽気に満ちた人波を縫って歩いている姿が印象的だった。ボクが勝手にそんな印象を受けているだけ、あるいは勝手なイメージを押し付けているだけの話なのかもしれないが、他人事ではないたまらなさがそこにはあって。同じ場所にいるのに違う世界を歩いているような。絶対的な悲愁。埋まらない孤独。分け合えない寂寞。歳を重ねることの凄絶さが本人の与り知らないところで尾を引いて、四散して、色を奪って。漂うその冷たさに息をのむ思いだった。
2018年5月15日のその日。美術館が位置する見慣れた公園の芝生には無数のテントが組まれたいた。
テント内に敷き詰められたイスにはすでに大勢の人が待機していて、その時を待っていた。
ほどなくして時間がくると、順々に案内を受け、すぐ横の美術館内へと誘導され、一般献花が行われた。
葬式だとかお別れ会の類いは、基本残された人の慰め以外の何ものでもないとボクは思っているので、綺麗事はよして本意をいえば、とにかく自分のなかの動揺を和らげるためこの場に足を運んでみたものの、いざ献花を終え、その場をあとにしたところで、正直いって何の意味もなく。
“高畑勲が死んでしまった”
ただそれだけの事実が、青白かったその日の空を一層白々と映すばかりで――。
人は死ぬ。いや、生きとし生けるもの、カタチあるものはみんな死ぬ。尽きる。
自分はもちろん、自分の周りの人や、自分をつくった全ての人、全ての動物、生物、目の前の景観、世界全部、地球、そして宇宙そのものも。順番こそまちまちだが、漏れることなく全てはいつか消失する。無に還る。
どうやらそういうことになっていて、それは当たり前のことである。当たり前のことなのだが、そんな日の訪れが想像も実感もできないような日常のなかにあって、自分の足場が日一日と確実に崩れていくというその現実は、ボクのなかのバランスを層一層と奪っていき、そうして、日毎歳を重ねることの難儀を思い知る。
“通りゃんせ 通りゃんせ
ここはどこの細道じゃ
天神さまの細道じゃ
ちっと通して下しゃんせ”
“行きはよいよい 帰りはこわい
こわいながらも
通りゃんせ 通りゃんせ”
図らずも自分が踏み込んでしまったこの “天神さまの細道” も帰り道に差し掛かった、あるいは帰り道に入っているということは間違いない。
折り返しのコーンを回るようにコペルニクス的転回は起こり、何が起こるかわからないからこそ楽しかった人生は、何が起こるかわからない不安に脅かされる人生にその景観をかえ、他方、何が起こるかわからないからこそ活気に満ちた足取りも、何が起こるかわかってきてしまったような諦念にその力を奪われていく。
近くに声を掛け合える人はいるが、互いの道は交わらず、思いを真に共有することもできず、いつ途絶えるかもわからないこの道に惑いながらも、それでも進むことを強いられて、低下していく体力に足取りは重く、折れる心に呼吸は乱れ、くだりになっているらしいその道で、心ならずもペースが上がれば、息苦しさにパニック寸前......。嗚呼、なんてタフなこの復路。
ともあれ、10年ごと区切られた部屋を通過するようなこの人生。明かりのある部屋は一つ。そこを目指し、進み、通過する若年期を過ぎ、その部屋の後光を頼りに暗がりの道を進む今。
先を進む先輩方の背中が消えてしまう心許なさは筆舌に尽くし難い。
博覧強記の高畑勲さんなら――。この世から消えるその瞬間のこと、気持ち、体感、その光景等々、卓抜した洞察力と豊かな描写力で体験したそれを表現し、ある種の指針を示していただくことも可能であったに違いないのだが、いかなる天才も死人に口無し。頭に輪っかを浮かせて「やぁ」と現れ、死んだ感想を述べるというような、その手のサポートは一切やっていないということであるからして、ゆく道は徹底的且つシビアである。
趣味や娯楽なんかの文化装置の効きも今一つ期待出来ないというか、懐疑的というか、そういう自分のなかの “ごまかし” もどんどん手薄になっていってる感じのある現状。末恐ろしくも孤独なこの帰り道を、はたしてボクはこの先堪え忍ぶことができるのだろうか。どう堪え忍べばいいのだろうか。どう堪え忍ぶべきなのか。あるいは、上記諸々に見て取れる自分の中のいかんともし難いナルシシズムをどう制御すればいいのか、どう向き合っていけばいいのか。そんなことをグルグル考えるだけの余裕が自分の中にあるということそれ自体が、恵まれたことなのか、身に余ることなのか、奢侈なことなのか......。
よろめく足にまごつきながら、今日もボクはこの道を進んでいく。
|
|
|
|
|
|
#31『マメが芽をだし、花となる』 <
| MAIN PAGE |
> #29『猪突妄信』
|
|
|
|